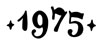DOVE SURFING WETSUITS
DOVE SURFING WETSUITS
最近流行りのフロントジップ。
ダブウエットスーツでは80年代から販売している代表的モデル。
フレックスジップと、インナー構造により動きやすさと防水性の融合。
ダブウエットスーツのおすすめモデルとなっています。
各モデルのカスタムオーダー受付中。お気軽にお問い合わせください。
INTRODUCTION
モダンサーフィンが日本に伝わってきたのは1960年代の初めのことだった。
そして’70年代を迎える頃には、湘南や千葉に幾つかのサーフボード・メーカーが生まれ、やがて日本の各地にも確立されていった。
それでもまだ、サーフィン専門といえるウェットスーツ・メーカーは存在せず、サーファーは、海外から輸入されたものか、ダイビングスーツ・メーカーが、3ミリの生地で製作したもので我慢するしかなかった。素材自体も今日とは次元が違うほど劣っていたが、それでも裁断や縫製など、改良の余地はあった。バリエーションも、わずかにタッパ、ビーバーテール、ロングジョン、ショートジョンといった程度でしかなく、寒さを凌ぐには、重ね着をするしかない時代だった。
あの頃の多くのサーファーにとって夏以外の季節は、今から思えば混雑と無縁な至福の季節だったといえるかもしれないが、寒さと動きにくさに耐えなければならない受難の季節だったのである。
’74年から’75年にかけての冬のハワイ。’60年代にサーフィンと出逢い、その虜になっていたひとりの男がいた。 ホームグラウンドの湘南を中心にして、海部をはじめ日本の素晴らしい波を求めた旅をし、各地のサーファーとも交流を深めていた彼だったが、25歳という年齢を迎えて、サーファーとしての自分の生き方も、ひとつの節目を迎えていると感じていた。
「仲間と一緒に、サーフィンで暮らしをしていきたかった。けれど、それまで自分の力になってくれた先輩達と衝突するようなことはしたくない」
あの頃、サーフィンで暮らすといえば、サーフボードファクトリーかサーフショップを始めること。しかし、それもなんとかやっていけるようになったばかりだった。彼はそれまで親交を結んできたサーファー達と、どこかで対峙することになりかねないような仕事を始めたくはなかった。だが彼は、サーフィンで暮らしていきたいのだ。
そして彼、戸倉康守は、サーファーである自分達が欲しい機能とデザインを追求する、サーフィンのためだけのウェットスーツ・ファクトリーをやってみようと思い立ったのだ。帰国した彼は、ダブ・サーフィング・ウェットスーツを設立。
そのネーミングの由来は、24フィートのヨット、ダブ号で世界一周単独航海に船出した少年が、5年の歳月をかけて5万6戦海里の冒険航海を達成するまでの実話をもとにした映画『DOVE/ダブ』からだった。ダブ号のように、自分達の作るウェットスーツが、世界中の波の上で、サーファーにとって最高のパートナーとなれるよう、そんな思いの込められたネーミングだったのだ。
そうして1975年に産ぶ声を上げた、ダブ・サーフィン・ウェットスーツ。創立以来、サーフィンを、ただ単にスポーツだとかコンペテションというようにカテゴライズできるものではなく、生まれてある悦びの最上のひとつと考えてきたダブは、その全人格をサーフィンに注ぎ込んで歩んできたつもりである。
それから30年。人間は、自分達の手が加えられた環境や、人間を甘やかすような環境にばかり浸っていると、世界全体が人間のために用意されているのだという錯覚に陥る。人間は地球のほんの隅っこを借りて住んでいるにすぎないのに、まるで主であるかのように振る舞う。その結果のひとつが、今の日本の海岸線だ。
それを痛みと感じられるサーファーであっても、そんな錯覚とまでいかないものの、時に勘違いもあっただろう。ダブが30年の歳月をこえてやってこれたのも、すべて波という地球の恵みあってこそ。地球上の海のほんの隅っこに、寄せ来る波という悦びの世界があったからなのだ。波と出逢うということの大前提が、人間の意志を遥かに越えた自然の領域に属していることを、時として忘れてはいないだろうか。
30年の間に私達がサーフィンしてきた数え切れないほどの素晴らしい波のすべてにおいて、我々が波を当てたのではなく、私達は恵まれたのだということを。
そして、30年の月日を経た今日、ダブが最高のサーフィング・ウェットスーツ・メーカーとしてあるのもまた、 そんな私達のポリシーを理解し、評価してくれるサーファー達がいたからだということも、私達は忘れない。ダブの仕事には、素晴らしいサーファーというパートナーの存在がなくてはならないからだ。そんな素晴らしいサーファーと共に未来へと、私達も歩んでいきたい。
OUR HISTORY 1975-2005
| 1975 | ダブ創設 |
| 1976 | 日本初のサーフィン専門誌サーフィンワールドの登場によりにわかにサーフィンが一般に広まりを見せる。その頃新しいタイプのウェットスーツが当時地形の決まっていた酒匂川河口でテストされていた。 |
| 1977 | この年、創立当初から開発が進められてきたショートスリーブ/ロングショーツ(シーガル)、ショートスリーブ/ショートショーツ(タートルスーツ)の製品化に成功する。今日では一般的な名称となっているが、シーガルスーツ、タートルスーツの名称はもともとはDOVEのオリジナル・モデルネームであったのだ。また、後に『デカダブ』と呼ばれ、チームの象徴ともなり、若きサーファー達の憧れともなった背中への大きなロゴマークプリントの登場もこの年のことである。 |
| 1978 | 8ー10フィートのノースショア・サンセットで、3日間にわたり行われたプロトライアルで添田博道が7位に入る成績を残し、ここに日本人によるノースショアアタックが幕を開けた。そしてこの年には、新たに肩ジッパー・デザインの開発が進められつつあった。 |
| 1979 | 9月、静波で開催されたJSOプロアマコンテストでは添田博道、青田琢二のワン・ツー・フィニッシュに加え、当時15歳だった久我孝男が並みいるプロを抑えて3位に入賞するという成果を上げた。またこの年、タイフーンスウェルを追って四国、九州とサーフトリップを続けたダブチームは、チームにとっても、添田にとっても初めてとなる、サーフィンワールドの表紙を飾ることとなった。さらに、スウェルに恵まれたこのトリップでは、ウェットのテストに充分な時間と波を得ることが出来、ついに肩ジッパーのデザインがこの年完成した。 |
| 1980 | チームの重鎮となる蛸操が参画。プロコンテストでは海部マスター造道卓がチューブを制し、貴重な勝利を挙げる。また、田川昇の招きで初めて北海道・イタンキ浜でのサーフィンを体験する。あまりの水温の低さに驚き、この時、この北海道で通用するウェットスーツこそ本物のウェットスーツだと痛感した。そして、この年から極寒地用ウェットスーツの開発に着手することになる。 |
| 1981 | 戸倉康守によって国内にトライフィンが初めて登場、ネットワークを通じて日本国中を駆け巡る。またサーフムービー『アジアン・パラダイス』撮影開始。添田博道、蛸操、市川武昌、戸倉康守の4名のサーファーそして、サーフィン・クラシック編集長の石井氏によるニアス島サーフトリップ。この旅のジャングルでの生活は全員に強烈なカルチャーショックを与え、これが今後の海外ハードコア・サーフトリップの原点となった。 |
| 1982 | 久我孝男プロデビューを劇的勝利で飾る。一方ガンストン500へ出場のため、久我孝男、蛸操、戸倉康守、植田義則は、初めての南アフリカ・ジェフリーズベイへトリップを行う。そしてこの年、遂にパイプラインの目の前に家を構えたダブチームは、ノースショアという大きな目標に向かい、本気の取り組みを開始した。その家は、『DOVE HOUSE』と名付けられた。 |
| 1983 | 久我孝男、プロ2年目でグランドチャンピオン。台風シーズンの九州ではパーフェクトレフトに遭遇。さらにコンペティションシーン以外のムーブメントとして、サーフィン・クラシック誌の映画撮影のためインドネシア・ツアーが重ねられ、チームからも多くのサーファーが参加した。 |
| 1984 | 柳沢純一、今須伸政、プロ初優勝。大混戦のJPSAサーキットを制して添田博道がグランドチャンピオンに。また秋のプロクラス・トライアルでは中村大輔、松尾博幸、杉本忠昭らがプロにステップアップする。制作が進められてきたサーフィン・クラシック誌の映画『アジアン・パラダイス』もこの年遂に完成した。 |
| 1985 | JPSAサーキット全6戦中4勝、日本国内のコンペティションシーンは久我孝男の時代を迎える。一方、フリーサーフィンでは西湘の西の河口が爆発。初めてのフォトセッションとなる。千葉ではドカリがこの時期テイクオフから掘れあがるチューブになり、カルビン・前田がサーフィン専門誌の表紙を飾ることになった。また、この頃開発された画期的な『カラースキン』の登場により、冬の黒一色だったポイントの風景は、明るい華やかなイメージへ生まれ変わった。 |
| 1986 | チームのサーファーが国内サーキットで大活躍、ファイナルトップ16に7名の選手が入る。一方、海外サーフトリップでは、増田昌章、中和房、千葉公平、戸倉康守がフォトグラファーの木本直哉とペルーに向かう。乾ききった不毛の大地を背景にした不思議なパラダイスを国内に初めて紹介した年であった。 |
| 1987 | ノースショアのダブハウスで養われたハワイアンとのコミニュケーションにより、今須伸政はパイプマスターズでも、その存在感をアピールする。またこの冬に撮影された新居秀男の写真は『サーフィンワールド』『サーフィンライフ』両誌のカバーとなり、数々のノースショアにおけるベストショットとしてダブチームのサーファー達が紹介される。ダブハウスの成果が様々な形となって表われ始めた。一方ではコンペティションシーンを離れて新たに掲げられたチームのテーマ、ハードコアサーフィンの追求が始まる。 |
| 1988 | グランドチャンピオンは千葉プロV6と共に4年連続で久我孝男の手に。最強チームは新たな道へ。また、チームとしては、ハードコアサーフィンの追求、そしてサーフトリップと、新たな目標への軌道修正となった一年。ディーン・ケアロハの招きによる、添田博道、増田昌章、そしてフォトグラファー近藤公朗のタヒチトリップ。そしてウエスタンオーストラリアには今須伸政、谷内太郎がフォトグラファー木本直哉と共に向かうなど、それまで日本人によって紹介されていない処女地へとチームはサーフサファリへ向かって行った。 |
| 1989 | 10年ぶりの茅ヶ崎西浜、圧巻だった勝浦のサンドラ。素晴らしい波を求めて活動は加速した。一方、トップサーファーの離脱によりショックを受けた戸倉康守は、ハワイで負った足の傷と、心の傷を癒すため、リハビリを兼ねロングボードを携えカリフォルニアへと6ヶ月の旅に出た。そしてこの旅が90年代に向けてのDOVEの新しい方向性を追求する旅となった。 |
| 1990 | 世界アマチュア選手権メンズで福地孝行がグランドファイナル進出、7位という快挙を成す。また、この年の仁淀川河口の波は79年にサーフィン雑誌に特集されて以来、今日に至るまでのベストショットである。その波に巡り会えたのが、蛸操、福地孝行だった。また、春のプロクラストライアルでチームに久々にレディースプロ・永井貴美が誕生した。 |
| 1991 | 台風シーズンを前にして地形が決まった四国の河口。チームのサーファーは縦横無尽に駆け回った。つまり日本の、いや地球上の素晴らしい波を求めて、当たる当たらないは別として常に東奔西走していると言う事だ。 |
| 1992 | フランス・ラカナウビーチでの世界アマでは、メンズクラスで脇田貴之が9位入賞を果たし、近い将来チームの中心となる予感を思わせた。さらに今年の台風シーズンは素晴らしい波に恵まれ、今まで考えられる限りのハードな条件でのテストを繰り返し、新素材を採用したモデルを製品化した年となった。それが、ニューロ39である。 |
| 1993 | グランドチャンピオンのタイトルを城純が、福地孝行も2位となり王座奪回をワンツーフィニッシュで決める。また、チームの選手もそれぞれが海外トリップで地球上の楽園を求めた旅をおこなった。ノースショアでは脇田貴之のパイプラインアタックが日本のサーフィンメディアに大フィーチャーされた年でもある。そしてこの年、冬の極寒・北海道でもサーフィン出来るウェットデザインであり、常に腕周りの動きを第一に考え、コイルドライジッパーを使用したマニアックモデルが、テストにテストを重ねた末に生み出された。 |
| 1994 | 国内プロサーキットシーンではダブチームが2年連続の1、2フィニッシュ。またこの年、バリを起点にチャーターした65フィートのヨットでクルーズしつつ、チームの7人の男達がインドネシアの島々でサーフィンしたボートトリップは、後に日本中のサーファーから注目を集め、今日のメンタワイ、モルディブ、ロンボク、フィジーと、もう一つの新しい形のボートトリップ&サーフエリアの火付け役となった旅となる。 |
| 1995 | ハレイワインターナショナルJr.で大野仙雅が優勝。福地孝行は世界を目指し、20周年を迎えチームの活動は益々躍進。さらにレディースで造道生はグランドチャンピオンに輝き、全日本アマではジュニアで牧野優介が優勝。また、この年はダブスタッフによる新素材テストの結果、ハニカムスキン、ニューロチタニウムという新しく軽い新素材によるウェットスーツを開発。新時代のパフォーマンス・ウェットスーツの幕開けとなる。 |
| 2005 | ダブ創設30周年を迎える。 |